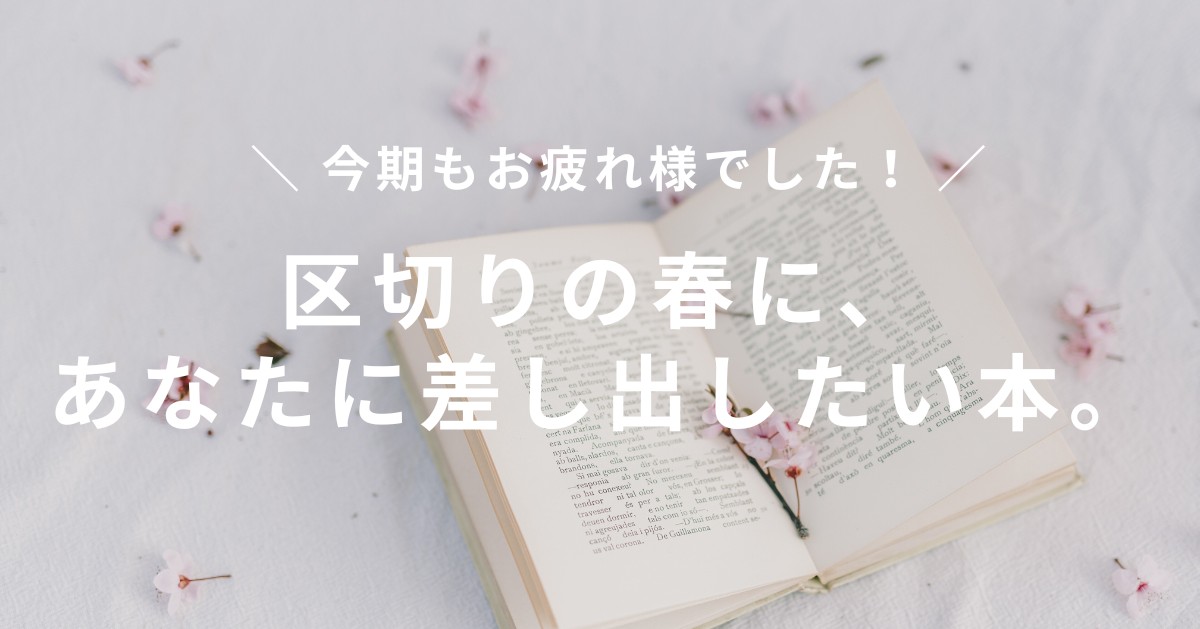#6 世界から本が消えるなら。
はじめに。
昨日は東北を中心に地震がありましたね。私は東京の自宅でひとりで、結構心細い気持ちがしたのですが、震源に近い方々のことを考えると心配です。何ができるということはないのですが、どうか皆無事であるとともに、余震などにも引き続き気をつけてくださいね。わたしも、気をつけます。
こんばんは、Akaneです。今は、コーヒーに豆乳を入れてを飲んでいます。72%カカオのチョコレートを一緒に。夜だから、ほんとはおやつ控えめ推奨なんだけども🙄ハイカカオなので許されたい←甘い
さて、今回も、疲れていたら適度に、気持ちがノッていたらじっくりと、いい感じのペースでご覧くださいませ。
明日はいつまで?
友達と、いまは人生100年時代で、まだまだやりたいことも、やれることも、やらなくてはならないことも沢山あるけど、明日がいつまでかっていうのは、誰も知らないねって話になった。
その大事な友達は、この前事故にあってしまった。幸い、大きな怪我には至らなかったけれど(本当によかった)、その体験をしたばかりの彼女の口から出たこの話は、リアルだった。明日が必ずやってくるようなつもりでいるけれど、その確率は100%じゃないってことをなんだか再認識したのでした。
それで、思い出したのが重松清さんの『その日の前に』。

この本は、人生最後の「その日」を迎えるまでの物語がいくつも詰まった短編集。先に申し上げておきますが、多分、泣いちゃいます。おうちで読む方がいいかも...
インドの独立を導いた、マハトマ・ガンジーは「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい」という言葉を残しているんだけど、まあここまで切羽詰まらないにしても、明日が来ないことだってあるかもしれない、ということと、学ぶってずっと自分を助けてくれるものなんだ、っていうことを、頭の片隅においておきたいな。
世界から本が消えるなら。

本の中では、世界からいろんなものが消えている。
有名なところで猫が消えた。川村元気さんの『世界から猫が消えたなら』は映画化もされたので覚えている人も多いのではないかしら。
文字が消えるのは、筒井康隆さんの『残像に口紅を』。(ちなみに元ネタになっていると言われているのが、冨樫義博さんの名作漫画『幽遊白書』の蔵馬、海藤というふたりの登場人物による、五十音順に1分ごと、1文字ずつ禁句が増えていくルールのゲーム)
「あ」が使えなくなると、「愛」も「あなた」も消えてしまった。
なんて、なんて小説的なんだろうって思った本だった。現実をリアルに追って、まるで体験しているかのように引き込む作品も好きなんだけれど、こんな風に、文字が消えてゆく、なんて、実際にはありえない世界を楽しめるのもまた、創作の特権だなと思う。
この小説は本当に実験的な小説で、最初の章で「あ」は早々になくなるんだけど、その後、この小説の中では「あ」という文字は登場しない。(私が登場人物の場合、すぐに名前が失われてしまうわ)
そうやって失われていく文字によって、日本語の持つ微妙なニュアンスが少しずつ変わっていく。でも、この本のすごいところは、文字が消えても、ほとんどない文字を使って、ギリギリのところで物語でいつづけられたこと。最後まで小説であるアイデンティティを失わずにいたこと。
これは筒井康隆さんの筆力以外の何物でもない。あって当たり前のものがない。そういう中でも生きていることがすごい。タイトルの意味も探りたくなる一冊です。
ということで、今日のレターでは「世界から本が消えるなら」、と題して、消えゆく本の中でこの先5冊だけ持つことが許されたという謎の状況において、残りの人生連れていきたい子たちをご紹介します。
うーん、結構迷った🤔けど、これに決めました。(漫画も含めたかったんだけど、1冊完結ものが少ないので今回は除外)

1冊目:残像に口紅を(筒井康隆)
ふたりはしばらく笑った。「いずれ『わ』がなくなると、笑うこともできなくなるんだな」
当たり前のものがないということ、想像を超えることの意味、文字を失っても最後まで物語であり続けること。ある意味、物語の内容以上に本が本であろうとしている姿が、人が生きる上で自分が自分であろうとする足掻きみたいな部分と重なった。物語じゃなくて、その存在をこの先も持っていたいという意味で選んだ。
そして、冒頭の話題とつながるけれど、いつまでもあると思うな、当たり前。いま、居ること、在ることが貴重である、という戒めも込めて。
2冊目:困難な成熟(内田樹)
身体という自然に絶えず「これで、いいんだよね?」と自問しながら僕は労働しています。そこからあまり離れないようにしています。(中略)この場合の「自然」は別に海や山や森の中という意味ではありません。ご自身の身体という自然の近くで労働してください。その仕事をしていると、生きる力がなんとなく高まるような感じがする仕事をしてください。
以前も紹介した私の中の座右の書。紹介するにあたり読み返したけど、相変わらず面白かった。といっても「全部賛同」という意味じゃなくて、共感も、違和感も全部含めて自分の頭が反応して考えるための書。折り目をめちゃくちゃつけた本。
迷ったら戻ってこれる本というのを1冊持っておくというのはとってもいいよ。
ひとには話せないことって、誰しもあるじゃない。話題的にっていうことじゃなくて、ニュアンスとか、細かいところまで誰かと「分かり合う」っていうのは難しくて、一番それを知ってるのは自分なので、そのニュアンスに近い本が見つけられると、きっと本が助けてくれることもあるはず。
3冊目:武器になる哲学(山口周)
重要なのは、よくいわれるような「常識を疑う」という態度を身につけるということではなく、「見送っていい常識」と「疑うべき常識」を見極める選球眼を持つということです。
読んでいる最中に既視感を覚え、本棚見返したら既に買っていた、っていう2冊買ったパターンの本。(たまにあるよね)2度欲しいと思ったということはきっとまた欲しくなるので持っていくことにした。
広義の哲学という学問の中で発見されたこと紹介している本。辞書的に気になったら開くという使い方をしたい。哲学は年齢を重ねた人の方が必要とするので、残りの人生に持っていくなら、やっぱり必要だ。
「そんなの知ってるよ」と思った瞬間から学びの扉がガシャーンと閉まる、ソクラテスの「無知の知」は、大人になってからの方が大事。(と言う意味で伊坂幸太郎さんの小説『逆ソクラテス』は必見)
4冊目:僕は勉強ができない(山田詠美)
「どうせ、人って死ぬのかと思うと、将来ってどう言う意味があるのかって考えちゃうよ。理想をおいかけたって、体が消えちゃえば、それまでじゃない。ぼく、来る途中考えてたんだ。煙をつかむようなものだって」(主人公の少年)
「煙をつかむのに手間をかけて何が悪い。(中略)物質的なものなんぞ、死んだら終わりだ。それなら煙のほうがましだ。始末に困らないからな。困らないものがいったい何なのか、おまえにもその内、解る時が来るだろうよ」(主人公の祖父)
舞台は、1990年くらいになると思うから、ちょっと今との違いは感じるかもしれないけれど、でも、人間の普遍的な部分、特に「自意識」に問いかけた哲学要素を含んだ小説。登場人物が豊かで見ていておもしろい。
学生のときに買った本で、その時は主人公の秀美くん側に目がいっていたけれど、今となっては周りの大人側に注目したい。自分が年齢を重ねたからこそ、10代のあの時にいて欲しかった大人であろうと思うので、未来に持っていく本に選んだ。
5冊目:すばらしい日々 (よしもとばなな)
もしも、だれもが「自分のことは自分でしっかりやる、でも、愛するあなたはとにかくすこやかでいてほしい」と思える時代になったら、どんなにいいだろう。
よしもとばななさんのエッセイ。写真と多くはない文字で構成されていて、ひとつひとつの章は短い。そして、この本は、たった一つの章のために、この後の人生に持っていく本に選んだ。その章は「すこやかに」(p.52)
何気ない日常。いつもの風景。生きること。いなくなること。向かい合うこと。ありそうで、あること。なさそうで、ないこと。ぎゅっと詰まったお守りのような本。
コミュニケーションのあとがき
前回は「すれ違わないコミュニケーション」というテーマでしたが、お返事いただいたメッセージの中で、いくつかコミュニケーションが苦手です、というものがありました。中でも気になったのが、電話とか、直接会ってとか、その場ですぐに繋げないといけない会話が苦手というもの。
いや、それ、わかる。ちなみに、わたしはどうしようもなく苦手、というわけではないものの、話すのはあんまり得意じゃない。そんなわたしですが、会社員時代、プレゼンがうまいと言われていたんです。でも、みんなは知らない。私が一言一句違わずに話せるくらいに練習してきていることを。←要領いい方じゃないから、量でどうにかするタイプ
電話も得意じゃなくて、相当こころの距離の近い相手以外の突然かかってくる電話は、ほぼ出ません。とはいえ、仕事上そうもいかないこともあるので、基本的に電話ではマイルールとして、すぐに返答しないで「確認して追って連絡します」ということにしています。言うならば、逃げのコミュニケーションです。
でも、これをやり始めてから気持ちがとっても楽。自分が出そうとしている回答を、もう一度自分に問うてみる。中の自分が、うん、って言ったら、わたしも、うん、って答える。
コミュニケーションは、逃げてもいいと思う。(でも、反応は早めにかえすのがベター)もちろん、チャレンジしなきゃいけないときもあるけれど。
逃げたいなって思うことがあるひとは、多分、周りの目気になったり、自分をみる自分の目が厳しかったりするんだと思う。それは悪いことじゃない(むしろ大事な時も多い)。でも、たまにしんどいよね。そんな人にはこれを。

世界累計500万部の大ベストセラー『嫌われる勇気』です。知ってるよ〜って人も多いかな? でも、そうあるべくしてそうなった本なような気もする。持っている人は再読の知らせと思ってパラ見してみるのもいいかも。
売れている本や評価されている本というのは、そうなった経緯や意味がきちんとある。これが売れているってことは、みんなが困っているってことでもある。
調べてみると、2020年時点で世界500万部、約半分近くになる228万部が日本での発行部数。日本の本なのでもちろん日本が一番売れるのではあるけれど、純粋な数で言っても、やっぱ、みんな困っているってことだ。ひとりだけじゃない。
コミュニケーションって、伝える方にちょっと寄りがちだけど、受け取り方も大事だよね👀
それでは、今回はこのへんで。いつもよりちょっと長くなっちゃった。まあ、そんなときも🙄最後まで読んでくれてありがとうございました!
それでは、また次の日曜の夜にお会いしましょう👋
次回は!
親切をしてくれたひとに「お名前は?」と聞くと「名乗るほどの者ではございません」って去っていく。っていうシーンがなぜか物語ではよくでてくるけど、そんな(?)「ペイフォアード(恩送り)」について書きたいなと思っています。
みんなは最近、誰にもらい、誰に渡しましたか?

▼要望や感想・話したいテーマ、気軽に送ってください。とっても喜んでます🙌
もし面白いなーと思っていただけたら、お知り合いにちょこっとお話してもらったり、SNS等でシェアしてもらえるととっても嬉しいです!
すでに登録済みの方は こちら